Renaultが2026年からEV全車種でリン酸鉄(LFP)系リチウムイオン電池を採用する方針。これまで三元系。LFPは中国企業が技術や生産を押さえており、中国製EVの躍進を支える中核技術。正極材にニッケル(Ni)とマンガン(Mn)、コバルト(Co)を使う三元(NMC)系に比べてエネルギー密度が低いが、中国企業は搭載方法などに工夫して三元系と遜色のない航続距離を実現しつつある。BYDはLFP搭載の手ごろな価格の中国製EVを欧州に投入しシェアを拡大。
LFPとNMC、そのほかのバッテリをまとめておこう
三元系(NCM/NCA) 公称電圧 3.7V
正極材料にNi・Co・Mn または Ni・Co・アルミ酸リチウム
高エネルギー密度
低温特性が良い
出力特性が良い(パワーが出やすい)
高価
熱安定性が低い(発火、熱暴走)
LFP 公称電圧 3.2V
正極材料にLiFePO4(リン酸鉄リチウム)
安全性が高い
サイクル寿命が長い(数千回)
安価
この二つは外見では見分けるのは不可。電圧で判断する。パック電圧が3.7の倍数か3.2の倍数か、など。
リチウムポリマー電池 価格が高い
リチウムイオン電池の一種。電解液をポリマーゲルにして封入した薄型電池。
柔軟なパウチ型構造で、薄型・軽量にでき、形状自由度が高い。
公称電圧:約3.7 V(LiCoO₂系)。
エネルギー密度は高いが、膨張・発火リスクあり。
用途例:スマートフォン、ドローン、ノートPC、RC模型など。
リチウム金属電池
一次電池。非常に高いエネルギー密度。
負極に金属リチウムを直接使用。内部短絡・発火の危険があるため充電には不向き。
公称電圧:3.0〜3.6 V(化学系による)。
用途例:カメラ用CR123A、医療用ペースメーカー、メモリバックアップ電源。
リチウム金属2次なる)
負極に金属リチウム
サイクル特性が悪い。現状100回程度。Enpower Japanは300回を達成しソフトバックのHAPS搭載を狙う(2025年9月23日日経新聞)。
VTOL、ドローン活用を模索
全個体電池
電解質を完全に固体化した次世代電池。液漏れや発火のリスクが極めて低く、安全。
高エネルギー密度・長寿命・広温度範囲で動作可能。
負極に金属リチウムを再び使えるため、理論エネルギー密度が非常に高い。
公称電圧:3.5〜4.3 V(材料による)。
ただし、界面抵抗・製造コストが課題。
注意
電池の場合は、正極=Cathode、負極=アノードです。
電子管は陰極=Cathode。解説はこちら。
(この後、ChatGPTの答えをそのままPasete)
ナトリウムイオン電池(Sodium-ion Battery, SIB)
LIBに代わる次世代の二次電池。Liの代わりにNa
| 項目 | ナトリウムイオン電池 | リチウムイオン電池 |
|---|---|---|
| 主原料 | ナトリウム(海水から大量に得られる) | リチウム(資源が偏在、高価) |
| エネルギー密度 | 約100–160 Wh/kg(現状) | 約180–250 Wh/kg(一般的) |
| コスト | 安価(資源・材料ともに豊富) | 高価 |
| 低温特性 | やや劣る | 優れる |
| 安全性 | 高い(熱暴走しにくい) | 条件により熱暴走の危険あり |
| サイクル寿命 | 数千回レベル(改善中) | 数千回~一万回以上(成熟技術) |
💡 メリット
- 資源の豊富さと低コスト性
ナトリウムは地球上に豊富で、資源偏在リスクが低い。 - 安全性の高さ
熱安定性が高く、発火リスクが低い。 - 環境負荷が小さい
リチウム・コバルトなど希少金属の使用を減らせる。 - 低温環境での動作改善が進行中
特に硬炭素負極の改良により、-20℃程度でも動作可能に。
⚙️ 現在の課題
- エネルギー密度がまだ低い
ナトリウムはリチウムより重く、イオン半径も大きいため。 - 長期サイクル安定性の向上
材料の体積変化や電解液との反応による劣化を抑える必要。 - 産業スケール量産技術の確立
まだ実証段階~初期商用化レベル。
🏭 主な応用分野
- 定置型蓄電システム(ESS)
再生可能エネルギー(太陽光・風力)の電力平準化用途。
→ 高エネルギー密度よりも「安全性・コスト・寿命」が重視されるため相性が良い。 - 低コストEVや二輪車
航続距離が短くても良い地域輸送用EVなど。 - 非常用電源・家庭用蓄電池
コストパフォーマンス重視の用途で採用が進む。
🧭 世界と日本の開発動向
- 中国:CATL(世界最大手)が2023年にSodium-ion電池セルを量産開始。EV(例:奇瑞汽車「Sehol E10X」)にも搭載。
- 欧州:Faradion(英)、Tiamat(仏)などが商用化に向け開発中。
- 日本:住友電工、日立造船、東芝、リチウムエナジージャパン、などが研究開発を推進。
🔋 まとめ
| 観点 | ナトリウムイオン電池の位置づけ |
|---|---|
| 代替候補 | リチウムイオン電池の補完・低価格版 |
| 強み | 安価・安全・資源豊富 |
| 弱み | エネルギー密度の低さ・技術成熟度 |
| 将来性 | 定置型や低価格モビリティ用に有望 |
ナトリウム硫黄電池 (NaS電池)
🔋 基本構造と特徴
- 電極:
- 正極 → 硫黄(S)
- 負極 → ナトリウム(Na)
- 電解質:
- β-アルミナ固体電解質(β-Al₂O₃) … ナトリウムイオンだけを通すセラミック材料
- この固体電解質を日本ガイシが独自技術で製造・量産化
⚙️ 動作温度
- 動作温度は 約300〜350℃。
電極のナトリウムと硫黄は常温では固体なので反応しません。
約300℃以上に加熱すると、
ナトリウム → 溶融Na(金属液体)
硫黄 → 溶融S
となり、電解質(β-Al₂O₃)を介してナトリウムイオンが移動できる状態になります。
→ これにより高エネルギー密度の電池反応が実現します。
♨️ 高温維持のためのエネルギーについて
1. 運転中は自己発熱で温度を維持
NaS電池は充放電中にジュール熱(内部抵抗による発熱)を発生します。
この自己発熱が内部の温度維持に利用されるため、一度動作温度に達すれば、外部加熱はほとんど不要です。つまり、稼働中の保温エネルギー消費はごくわずかです。
2. 初期加熱(起動時)だけは外部エネルギーが必要
室温から300℃まで加熱するには、電気ヒーターで数時間〜十数時間かけて昇温します。これは設置時または長期停止後の再起動時のみ必要な工程です。
3. 保温構造が非常に優れている
日本ガイシのNaSモジュールは真空断熱構造を採用。外気温が変化しても内部温度が安定するように設計されています。放熱損失は総エネルギーの数%以下に抑えられています。
⚡ 特徴
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| エネルギー密度 | 高い(約150–240 Wh/kg) |
| 効率 | 約85–90% |
| サイクル寿命 | 数千サイクル |
| 課題 | 高温動作による安全管理・断熱・コスト面の課題 |
主な用途
- 電力会社の系統安定化(ピークシフト)
- 風力・太陽光発電の出力平準化
- 工場やビルの非常用電源
- 日本国内外(特に中東・欧州)に多数納入
- 日本ガイシは**「ナトリウム硫黄電池(NaS)」の世界的先駆者**。
- 現在の「ナトリウムイオン電池」とは電極材料も動作温度も異なる。
- ただし、ナトリウム利用電池技術の系譜としては、NaS電池の技術(特に電解質やナトリウム制御技術)は、Naイオン電池にも重要な知見を与えています。
- 現在も日本ガイシは定置型蓄電用途でNaS電池を製造・販売中(特に大型蓄電システム分野)。
エネセラ
「エネセラ(ENE-CELL, エネセラ株式会社)」は、少し特殊なタイプの電池を開発している日本企業です。一般的なリチウムイオン電池やナトリウムイオン電池とは原理や構造がかなり異なるのが特徴です。以下で、エネセラの電池技術の方式・構造・特徴をわかりやすく整理します。
🔋 エネセラ(ENE-CELL)とは
- エネセラ株式会社は、日本ガイシの社内ベンチャーとして2011年に設立された企業です。
- 日本ガイシが培ってきたセラミックス技術を応用して、
「全固体セラミック二次電池(セラミック蓄電素子)」を開発しています。 - 製品ブランド名も「ENE-CELL(エネセル)」と呼ばれます。
⚙️ 基本構造と方式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電池のタイプ | 全固体セラミック電池(All-Solid-State Battery) |
| 主な構造 | 電極も電解質もすべて酸化物系セラミックで構成 |
| 電解質 | 無機固体電解質(リチウムイオン伝導性酸化物) |
| 電極材料 | 特殊な酸化物系セラミック(電極と電解質が一体化) |
| 封止構造 | 樹脂や金属封止ではなく、セラミック焼結体そのものがセル構造 |
つまり、リチウムイオン電池のように「液体電解液」を使わず、完全に固体だけで構成された電池です。
🔬 特徴と利点
1. 超高い安全性
- 液漏れや熱暴走のリスクがゼロ。
- 可燃性の有機電解液を使用しないため、発火しない電池。
2. 広い動作温度範囲
- セラミック材料は熱安定性が高く、-40℃〜150℃程度でも動作可能(用途によって異なる)。
- 自動車や産業機器の厳しい環境下でも使用可能。
3. 長寿命
- 電極・電解質ともに化学的に安定しており、数万回レベルの充放電が可能とされています。
4. 極薄で高耐圧
- セラミック基板技術により、厚み 0.1〜0.3 mm 程度 の超薄型構造を実現。
- 曲げにやや弱いが、高温・高圧環境下でも安定。
⚡ 性能・用途(従来電池との比較)
| 項目 | エネセラ電池 | リチウムイオン電池 | NaS電池 |
|---|---|---|---|
| タイプ | 全固体セラミック電池 | 液系リチウム電池 | 高温ナトリウム硫黄電池 |
| 動作温度 | 常温〜150℃程度 | 常温(0〜60℃) | 約300〜350℃ |
| エネルギー密度 | 小〜中(数十 Wh/kg 程度) | 高(150〜250 Wh/kg) | 高(150〜240 Wh/kg) |
| 安全性 | 非常に高い | 中程度(熱暴走リスクあり) | 高い(高温運転要) |
| 主な用途 | センサー、IoT機器、電子部品のバックアップ電源など | 携帯端末、EV、蓄電池 | 定置型大容量蓄電 |
| 再起動・メンテナンス | 不要(常温動作) | 不要 | 加熱必要 |
🧠 技術的コンセプト
エネセラの電池は、いわば
「セラミック基板そのものが電池になっている」
という発想で、電極・電解質を一体化焼結して作られます。
これにより:
- 接合界面が少なく劣化しにくい
- 製造が簡略化できる(印刷 → 焼結プロセス)
- 微小デバイスに直接実装できる
といったメリットがあります。
🏭 想定される応用分野
エネセラの全固体セラミック電池は、大電力用途ではなく、小型・高信頼性用途を狙っています。
- センサー・IoTデバイス(長寿命バックアップ電源)
- ウェアラブルデバイス
- 医療機器(埋め込み型含む)
- 高温環境で使う電子機器(自動車、プラントなど)
- スマートメータや非常用電源補助


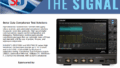
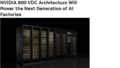
コメント